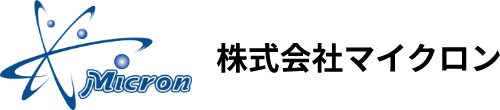はじめに
今回は、マイクロンのScientific Advisorを務めていただいている工藤與亮(こうすけ)教授にインタビューを行い、医療機器プログラム(SaMD)開発に成功した先駆者としてのご経験を紹介します。工藤教授は、北海道大学大学院医学研究院の放射線科学分野で画像診断学教室を率いています。先生が開発した自作プログラム「PMA」で株式会社マイクロンと協働し、医療機器認証を取得して上市、そしてそれがその後の開発にどう繋がったのかという一連のストーリーを、紐解いてゆければと考えています。インタビューは外部の専門家によって行われ、工藤先生の豊富な知識と実績を通じて、SaMD開発の現状と未来について深く掘り下げています。
さらに、「今、SaMD開発に何が必要なのか?」という問いに対して、工藤先生の洞察を交えながら、技術的なスキル、チーム構成、規制対応などの重要な要素を浮き彫りにしていきます。SaMD開発に関心を持つ皆様にとって、貴重な情報源となることを願っています。
ぜひ、ご覧ください。
工藤 與亮 教授

- 1995年
-
北海道大学 医学部医学科 卒業
- 2008年~2011年
-
岩手医科大学
先端医療研究センター 講師 - 2013年~2019年
-
北海道大学病院 放射線部
准教授、放射線診断科長 - 2019年~現在
-
同大学大学院 医学研究院
放射線科学分野
画像診断学教室 教授
- インタビュアー:
-
では工藤先生、まずは開発された「PMA(Perfusion Mismatch Analyzer)」についてお聞きします。これはどんな機能を持つプログラムなのでしょうか。
- 工藤教授:
-
これは急性期脳梗塞における脳血流の自動解析プログラムで、血管内治療(機械的血栓回収療法)の適応患者の選択支援にも使用できます。MRIの灌流画像(毛細血管の組織血流)と拡散強調画像(水分子の拡散運動)の異常領域を比較し分析評価するプログラムで、具体的には虚血ペナンブラ(可逆的虚血で救済可能な領域)と虚血コア(不可逆的梗塞で救済不可)の領域をカラーで示すことができます。
- インタビュアー:
-
この開発に至った臨床課題を教えて下さい。どんなきっかけで開発を始めたのですか。
- 工藤教授:
-
開発を開始した当時(2000年前後)からCTやMRIによる脳血流解析の原理は確立されていたのですが、各機器メーカーの解析ソフトで同じ画像を解析しても違う結果が出ていたのです。私は元々、医学部学生時代から趣味でプログラミングには取組んでいたので、それを自作のプログラムで検証を始めたのが最初でした。だから何か喫緊の臨床課題に迫られて行動したというより、好奇心とそれを満たす喜びが原動力だったと思います。放射線科医とプログラマーですので、今で言う“二刀流”ですね。
- インタビュアー:
-
確かに!ちなみにこれを開発されたことは、その後の研究にも活きていますか。
- 工藤教授:
-
そうですね。元々DICOM画像を様々に分析したかったのですが、当時はDICOM画像の読み込みすら大変だったので、ライブラリーを自作しました。これがPMA開発にも活きましたし、17O標識水をMRIの同位体ラベルとして用いるという別のプロジェクト(※)にも活きました。そういう意味で、教室の画像処理研究プラットフォームとして機能しています。
※北海道大学「リサーチタイムズ」記事:
https://www.hokudai.ac.jp/researchtimes/2021/04/1mri.html
- インタビュアー:
-
さて、では次に先生のPMAが、2019年に薬機法に基づく医療機器認証を取得した件について伺います。まず確認ですが、これは「承認」ではなく「認証」で、一定の基準に合致していたので治験は必要なかったということですか。
- マイクロン:
-
はい。したがって当社との協働では、通常のCRO(開発業務受託)業務ではなく、製造販売業として医療機器認証の申請を行いました。加えて、販売のパートナーとしても機能しています。
- 工藤教授:
-
その通りです。本当にしっかりした仕事をしてくれているので(北海道から遠いこと以外は…笑)全て満足で、信頼しています。私からも補足すると、PMAは2006年にフリーウェアとして公開して改善を重ねてきましたが、国内外で延べ2,000 人の登録ユーザさんがいらっしゃいまして、そのサポート対応に限界が来て、外部のプロにライセンスアウトしようと思い、イメージングCRO(画像解析を得意とするCRO)としてご縁のあった株式会社マイクロンにお願いしたのです。ですから今なお“絶えざる努力”を要するメンテナンスについても、とても助かっています。常に“想定しない使い方”をする人はいるもので、様々なユーザサポートや継続的なバージョンアップ、機能追加などが必要ですから。
- インタビュアー:
-
なるほど。では続いて先生の過去に遡ります。プログラミングは大学生時代からですか。
- 工藤教授:
-
いえ、中学時代からですね。当時は“マイコン”と呼ばれた機種を使って、機械語やBASICから始めました。プログラムができるようになったことで、医師となった今では、医療とは別の視点を持つ複眼になれたと思いますし、プログラマーの方と話す時も、上手く伝わるようになった気がします。
- インタビュアー:
-
そうして実際にSaMDを開発された訳ですが、感じたハードルとその乗り越え方についてはどうお考えですか。
- 工藤教授:
-
SaMD開発には大きく5つ、【機能を備え、それが有用で、不具合なく、結果もばらつかず、サポートも万全】であると、示さなくてはなりません。これらを全て、医師が十分にこなすことは難しいので、「信頼できるパートナー」が大事だと思います。そうした存在と上手く出会って交流し、信頼を醸成する上でも、医師がプログラムを学ぶ意義は大きいと思います。
- インタビュアー:
-
最後に、記事を読んでいる先生方に、メッセージをお願いします。
- 工藤教授:
-
まず、医師にプログラミングを学んで欲しい。そうすると、今まで解決できなかった臨床課題を自分で解決できるようになりますし、企業や情報系の方々とも臨床課題解決の方法について上手く共有できるようになる。今はプログラミングもだいぶ敷居も下がっていると思うので、ぜひ挑戦してみてください。そしてそれが出来る人には、ぜひ趣味のレベルを超えて、仕事として挑戦して欲しいです。さらにはスタートアップする人が増えるといいですね。とにかく海外に負けて欲しくないのです。
- インタビュアー:
-
熱い言葉をありがとうございました。私もこの取材で火が点いたので、先生に教えて頂いた北大のプログラム「医療AI開発者養成プログラム(CLAP)※」に早速申込みました。1年コースで全てオンライン(しかも無料!)なので、ご興味ある方はこちらから。
※医療AI開発者養成プログラム(CLAP):https://ai.med.hokudai.ac.jp/
本記事は民間医局コネクトで掲載されていた内容を、一部変更して転載しております。